先日、米国人の友人と久しぶりに話していたときのことだ。コロナ禍を受け、シリコンバレーから800キロほど離れた地方に引っ越したという。同時に牧場も購入し、牛や鶏を飼いながら2人の子供を育てるライフスタイルを実現したのだと話していた。
移住に合わせて前の職場を離れ、シリコンバレーの大手IT企業に就職したとも言っていた。そこでリモートワークをしながら、数カ月おきにシリコンバレーに通うという生活を送っているそうだ。
このように、コロナ禍をきっかけにリモートワークが定着したことで、物価が高い場所から引っ越しをする人はアメリカでも増えている。私の友人のように、一家で地方へ移住するようなケースもあれば、都心から少し離れた場所に引っ越しをするケースも多い。
米調査会社モーニング・コンサルトが実施した調査の結果によると、 87%の米国人がリモートワークを含めた柔軟な働き方を求めており、5割近くの人が何かしらのリモートワークが提供されない場合、職場を離れると回答した。
このように、従業員側の需要が大きいリモートワークだが、雇用主がその期待に応える準備が整っていない場合も多い。例えば、セキュリティーの環境を整えたり、リモートワークになることで評価制度を見直したりといったことだ。採用した人たちの業務指導や研修などをどうやってオンラインで行うかなど、特に人事部にとって見直さなければいけない事項が多いのが現状だ。
AIの活用提案から、ビジネスモデルの構築、AI開発と導入まで一貫した支援を日本企業へ提供する、石角友愛氏(CEO)が2017年に創業したシリコンバレー発のAI企業。
社名 :パロアルトインサイトLLC
設立 :2017年
所在 :米国カリフォルニア州 (シリコンバレー)
メンバー数:17名(2021年9月現在)
パロアルトインサイトHP:www.paloaltoinsight.com
お問い合わせ、ご質問などはこちらまで:info@paloaltoinsight.com

2010年にハーバードビジネススクールでMBAを取得したのち、シリコンバレーのグーグル本社で多数のAI関連プロジェクトをシニアストラテジストとしてリード。その後HRテック・流通系AIベンチャーを経てパロアルトインサイトをシリコンバレーで起業。東急ホテルズ&リゾーツのDXアドバイザーとして中長期DX戦略への助言を行うなど、多くの日本企業に対して最新のDX戦略提案からAI開発まで一貫したAI・DX支援を提供する。2024年より一般社団法人人工知能学会理事及び東京都AI戦略会議 専門家委員メンバーに就任。
AI人材育成のためのコンテンツ開発なども手掛け、順天堂大学大学院医学研究科データサイエンス学科客員教授(AI企業戦略)及び東京大学工学部アドバイザリー・ボードをはじめとして、京都府アート&テクノロジー・ヴィレッジ事業クリエイターを務めるなど幅広く活動している。
毎日新聞、日経xTREND、ITmediaなど大手メディアでの連載を持ち、 DXの重要性を伝える毎週配信ポッドキャスト「Level 5」のMCや、NHKラジオ第1「マイあさ!」内「マイ!Biz」コーナーにレギュラー出演中。「報道ステーション」「NHKクローズアップ現代+」などTV出演も多数。
著書に『AI時代を生き抜くということ ChatGPTとリスキリング』(日経BP)『いまこそ知りたいDX戦略』『いまこそ知りたいAIビジネス』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『経験ゼロから始めるAI時代の新キャリアデザイン』(KADOKAWA)、『才能の見つけ方 天才の育て方』(文藝春秋)など多数。
実践型教育AIプログラム「AIと私」:https://www.aitowatashi.com/
お問い合わせ、ご質問などはこちらまで:info@paloaltoinsight.com
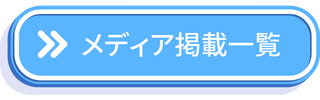 |
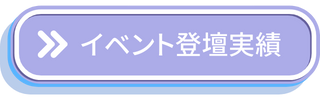 |
※石角友愛の著書一覧
毎週水曜日、アメリカの最新AI情報が満載の
ニュースレターを無料でお届け!
その他講演情報やAI導入事例紹介、
ニュースレター登録者対象の
無料オンラインセミナーのご案内などを送ります。