
コンピューターサイエンス分野でのノーベル賞として知られる「チューリング賞」を主宰する計算機協会(ACM)という学会がある。その機関誌に、興味深い論文が投稿されていた。米ボストン大、イスラエルのテクニオン工科大とテルアビブ大、イタリア・ミラノのボッコーニ大によるデータサイエンスと法律をかけあわせた共同授業開始に関する論文だ。
論文は言論の自由に関することから始まる。米議会では、通信品位法230条がしばしば議論になる。SNS(ネット交流サービス)などのプラットフォームは基本的にメディア会社とみなされず、ユーザーが発信、共有する情報について法的責任を問われないという法律だ。
しかし、フェイスブックから流出した利用者の膨大な個人情報が、英選挙コンサルティング会社のケンブリッジ・アナリティカによって米大統領選などに使われたとされる問題が起きて以降、プラットフォームの社会的影響力を踏まえ、中立の立場を主張して「言論の自由」を振りかざすSNSプラットフォームに対する規制が厳しくなってきた。
最近では、音楽やポッドキャストを配信しているプラットフォーム、スポティファイで、著名ポッドキャスターのジョー・ローガンが陰謀論信者の医師を番組のゲストに呼び、「新型コロナウイルスワクチンは国の陰謀策だ」と語らせたことが問題になった。
この番組は米国で一番人気があるポッドキャストで、毎回約1100万人もの人が聴いているという。また、スポティファイでの独占配信となっていることから、スポティファイにとって非常に重要な収益源ともいえる。
これだけの影響力を持つ番組で、偽情報を配信していいのかということが問題になったのだ。270人以上の医師や科学者らがスポティファイに署名を提出し、「プラットフォーム上の偽情報を抑制するための明確かつ公開されたポリシーの確立」を要請した。
スポティファイで音楽配信をしている多くのアーティストやミュージシャンも抗議した。ジョー・ローガン本人も謝罪し、問題となった回を削除した。
一方で、この件で本人以上に責任を問われたのが、即座に対処しなかったプラットフォーム側のスポティファイだった。同社は、今まで音声コンテンツ配信に特化した「中立の立場」のプラットフォームとして運営していたため、どんな情報が配信されているかのチェックには注力していなかったのだ。
前述の論文では、こういった問題がケーススタディーに即して紹介されている。例えば、架空のSNSがあったとして、そのアルゴリズム(コンピューターの計算や処理の手順)を作るデータサイエンスチームと、「このコンテンツはアウトで、このコンテンツはOK」という線引きを決めるため、コンテンツのチェックをする法務部が話し合いをする現場を想像していただきたい。以下は論文からの抜粋だ。
ある架空のSNSの法務部が「扇動的なコンテンツを削除する必要性」と「言論の自由」を適切なバランスに基づいてチェックするシステムを開発するようにデータサイエンスチームに依頼しました。
データサイエンスチームは「自分たちのアルゴリズムが扇動的なコンテンツの90%を削除できた」ことと、「削除されたコンテンツのうち、扇動的でないものは20%だった」ことを報告しました。ところが、サンプルを調査したところ、法務部はこのアルゴリズムが「明らかに扇動的でないコンテンツ」まで削除していたことを発見しました。
AIの活用提案から、ビジネスモデルの構築、AI開発と導入まで一貫した支援を日本企業へ提供する、石角友愛氏(CEO)が2017年に創業したシリコンバレー発のAI企業。
社名 :パロアルトインサイトLLC
設立 :2017年
所在 :米国カリフォルニア州 (シリコンバレー)
メンバー数:17名(2021年9月現在)
パロアルトインサイトHP:www.paloaltoinsight.com
お問い合わせ、ご質問などはこちらまで:info@paloaltoinsight.com

2010年にハーバードビジネススクールでMBAを取得したのち、シリコンバレーのグーグル本社で多数のAI関連プロジェクトをシニアストラテジストとしてリード。その後HRテック・流通系AIベンチャーを経てパロアルトインサイトをシリコンバレーで起業。東急ホテルズ&リゾーツのDXアドバイザーとして中長期DX戦略への助言を行うなど、多くの日本企業に対して最新のDX戦略提案からAI開発まで一貫したAI・DX支援を提供する。2024年より一般社団法人人工知能学会理事及び東京都AI戦略会議 専門家委員メンバーに就任。
AI人材育成のためのコンテンツ開発なども手掛け、順天堂大学大学院医学研究科データサイエンス学科客員教授(AI企業戦略)及び東京大学工学部アドバイザリー・ボードをはじめとして、京都府アート&テクノロジー・ヴィレッジ事業クリエイターを務めるなど幅広く活動している。
毎日新聞、日経xTREND、ITmediaなど大手メディアでの連載を持ち、 DXの重要性を伝える毎週配信ポッドキャスト「Level 5」のMCや、NHKラジオ第1「マイあさ!」内「マイ!Biz」コーナーにレギュラー出演中。「報道ステーション」「NHKクローズアップ現代+」などTV出演も多数。
著書に『AI時代を生き抜くということ ChatGPTとリスキリング』(日経BP)『いまこそ知りたいDX戦略』『いまこそ知りたいAIビジネス』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『経験ゼロから始めるAI時代の新キャリアデザイン』(KADOKAWA)、『才能の見つけ方 天才の育て方』(文藝春秋)など多数。
実践型教育AIプログラム「AIと私」:https://www.aitowatashi.com/
お問い合わせ、ご質問などはこちらまで:info@paloaltoinsight.com
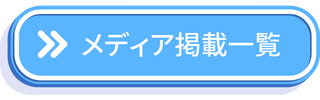 |
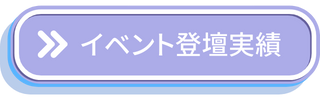 |
※石角友愛の著書一覧
毎週水曜日、アメリカの最新AI情報が満載の
ニュースレターを無料でお届け!
その他講演情報やAI導入事例紹介、
ニュースレター登録者対象の
無料オンラインセミナーのご案内などを送ります。