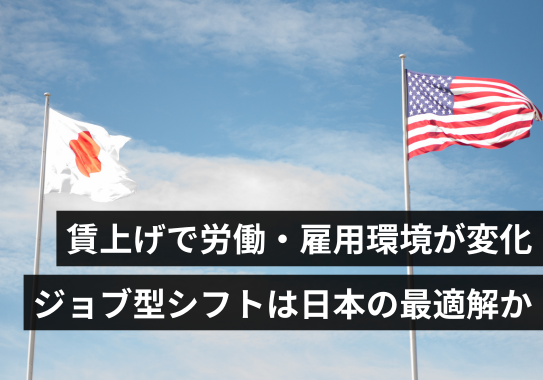
2023年に入り、大企業を中心に賃上げが活発化しており、日本企業の雇用形態も従来のメンバーシップ型からジョブ型雇用への転換を検討する企業が増えています。ユニクロの初任給を30万円に引き上げ、国内正社員の年収も最大40%増という発表などは大きく話題になりました。そこで、日本の雇用環境が変化している現状や、アメリカの雇用環境との違い、日本が目指すべき姿などについて焦点を当てて紹介していきます。
? この記事から得られる3つのポイント
・日本とアメリカの雇用環境の違いについて
・ジョブ型のメリット、デメリット
・アメリカでのレイオフ・解雇の捉えられ方
現在、大企業を中心に賃上げが活発化しており、日本企業の雇用形態も従来のメンバーシップ型からジョブ型雇用への転換を検討する企業が増えているようです。今年1月には、ユニクロが初任給を30万円に引き上げ、国内正社員の年収も最大40%増と発表し、大きく話題になりました。
特に注目しているのは、雇用制度を変革し、個人の成長や業績貢献を反映させようとしている企業が増えてきていることです。例えば、ソニーグループでは、AI分野などで賃金水準を改めており、トヨタ自動車、富士通、日立製作所でも本体とは異なる賃金体系を導入しています。また、国内外の社員を対象とするジョブ型雇用制度への移行も進んでいます。
大手企業の賃上げや雇用制度が移行している背景は、日本が他の主要国と比較して、給与制度の柔軟性が不足していることや、業績に貢献した優秀な人材に対して多くの賃金が配分できない課題にあると思われます。これまでは国際的に競争力のある人材の獲得が難しかったのですが、雇用制度をジョブ型へ改めることで、給与水準を引き上げやすくなり、優秀な人材を獲得する国際競争において巻き返しを狙う意図があると考えられます。
日本と同様にアメリカでも賃上げの動きは進んでいます。ただ、現在のアメリカの賃上げは、需要と供給のバランスによる経済原理の一面が大きいです。高齢者の早期引退や、移民の減少など、単純に労働者の供給が不足していることが原因として挙げられます。
労働力不足により賃金が上昇することで、結果としてサービス価格までも上昇しています。最近では、物価上昇を賃金に反映させる動きが見られます。例えば、一部の企業では、物価の上昇を賃金にスライドさせるCOLA条項(Cost-Of-Living Adjustmentsの略称で、インフレなど生活費の上昇に応じて賃金を引き上げる方式)を採用しています。賃上げをめぐる労使交渉や労働組合を立ち上げる動きも活発化しており、組合設立の認定件数も大幅に増加しています。
日本とアメリカの違いで言うと、人材の流動性が高いという特徴も関連していると思います。そもそもアメリカではジョブ型での雇用が一般的で、給与形態は学位やスキルに応じて決まります。日本の新卒一括採用のように、会社の中で育て、経験年数に応じて給与を支払うよりは、会社の経営状況に合わせてその都度人員を募集し、スキルや学位に応じた給与を提示する仕組みが一般的です。また、労働市場も自由化されており、アメリカでは、労働者と企業の契約のほとんどが「Employment at will(エンプロイメント・アット・ウィル)」と呼ばれる原則に基づいています。これはいつ、いかなる理由でも、雇用者または従業員が自由に解雇、または退職できるというもので、この原則により、企業は需要や生産性に応じて労働力を調整することができるのです。
日本のメディアでもアメリカのレイオフについてよく報じられていますが、レイオフや解雇といった行為は日常茶飯事であり、アメリカ社会では特段珍しいことではありません。
AIの活用提案から、ビジネスモデルの構築、AI開発と導入まで一貫した支援を日本企業へ提供する、石角友愛氏(CEO)が2017年に創業したシリコンバレー発のAI企業。
社名 :パロアルトインサイトLLC
設立 :2017年
所在 :米国カリフォルニア州 (シリコンバレー)
メンバー数:17名(2021年9月現在)
パロアルトインサイトHP:www.paloaltoinsight.com
お問い合わせ、ご質問などはこちらまで:info@paloaltoinsight.com

2010年にハーバードビジネススクールでMBAを取得したのち、シリコンバレーのグーグル本社で多数のAI関連プロジェクトをシニアストラテジストとしてリード。その後HRテック・流通系AIベンチャーを経てパロアルトインサイトをシリコンバレーで起業。東急ホテルズ&リゾーツのDXアドバイザーとして中長期DX戦略への助言を行うなど、多くの日本企業に対して最新のDX戦略提案からAI開発まで一貫したAI・DX支援を提供する。2024年より一般社団法人人工知能学会理事及び東京都AI戦略会議 専門家委員メンバーに就任。
AI人材育成のためのコンテンツ開発なども手掛け、順天堂大学大学院医学研究科データサイエンス学科客員教授(AI企業戦略)及び東京大学工学部アドバイザリー・ボードをはじめとして、京都府アート&テクノロジー・ヴィレッジ事業クリエイターを務めるなど幅広く活動している。
毎日新聞、日経xTREND、ITmediaなど大手メディアでの連載を持ち、 DXの重要性を伝える毎週配信ポッドキャスト「Level 5」のMCや、NHKラジオ第1「マイあさ!」内「マイ!Biz」コーナーにレギュラー出演中。「報道ステーション」「NHKクローズアップ現代+」などTV出演も多数。
著書に『AI時代を生き抜くということ ChatGPTとリスキリング』(日経BP)『いまこそ知りたいDX戦略』『いまこそ知りたいAIビジネス』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『経験ゼロから始めるAI時代の新キャリアデザイン』(KADOKAWA)、『才能の見つけ方 天才の育て方』(文藝春秋)など多数。
実践型教育AIプログラム「AIと私」:https://www.aitowatashi.com/
お問い合わせ、ご質問などはこちらまで:info@paloaltoinsight.com
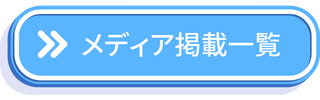 |
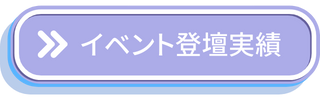 |
※石角友愛の著書一覧
毎週水曜日、アメリカの最新AI情報が満載の
ニュースレターを無料でお届け!
その他講演情報やAI導入事例紹介、
ニュースレター登録者対象の
無料オンラインセミナーのご案内などを送ります。