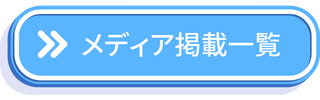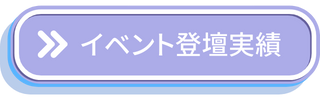|
マイクロソフトは自社の生成AI技術を現場に積極的に導入し、業務効率化を推進しています。その一方で、エンジニアやカスタマーサポート部門に対する大規模なレイオフを実施するなど、人員再編にも踏み込んでいます。AI活用と人員削減という二面性を持つこの動きは、業界全体に波紋を広げており、企業経営や労働市場に対するAIの影響が現実のものとなりつつあることを示しています。
副社長のジェフ・ハルス氏が率いる400名規模のソフトウェアエンジニア部門では、現在AIが生成するコードの比率を全体の20-30%から50%に引き上げるよう指示が出たと報じられています。これは単なる補助的なツールとしてのAIではなく、開発の主力手段としてAIを位置づけようとする試みです。
特に注目すべきは、バグ修正やクラウドサーバーの障害対応を担うエンジニアたちに対して、もはや従来のコーディングスキルではなく、「AIプロンプトエンジニア」としてのスキルを求めている点です。つまり、AIに対して適切な指示を与えて成果を最大化することが求められるのです。
またマイクロソフトでは、エンジニア部門にとどまらず、営業やカスタマーサポートにおいてもAI活用を徹底しています。営業部門では、Chief Commercial Officerのジャドソン・アルトフ氏の指揮のもと再編が行われ、各法人顧客に対して一人の担当者が統括する体制に変更されました。背景には、AIツールを活用することで、担当者が幅広い製品知識を迅速に習得し、多岐にわたる業務をこなすことが可能になるという期待があります。
このことから、今後は既存の「認知労働」がAIによって置き換えられるだけでなく、新たな「認知労働」がどのように生まれ、どのように人材が再配置されるのかが問われることになります。ナデラCEOの「認知労働は自動化されるかもしれないが、次の認知労働が生まれる」という発言は、その可能性と希望を示すものといえるでしょう。企業にとって、AIをどのように取り入れるかだけでなく、AIが変える働き方や組織の在り方にどう適応していくかが、今後の成長の鍵です。
記事元:https://www.theinformation.com/articles/behind-microsoft-layoffs-automation-efforts-boom?rc=pdkxfw&shared=ce88893aef6568ba
|